障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての人が分け隔てなく人格と個性を尊重し合いながら共存するために、平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されました。
この法律では主に、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者が「障害を理由とする差別」を行うことを禁止しています。
障害を理由とする差別とは
1.不当な差別的取り扱い
障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為のことです。
例えば、障害があるという理由だけで、スポーツクラブに入れない、アパートを貸してもらえない、車いすだからといって入店できないなどが該当します。
2.障害のある人への合理的配慮の不提供
障害のある人やその家族から、何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲での社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことです。
例えば、聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人に分かりやすく説明しないなどが該当します。
社会的障壁とは
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもののことです。
1.社会における事物
通行、利用しにくい施設や設備など
2.制度
利用しにくい制度など
3.慣行
障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など
4.観念
障害のある人への偏見など
行政機関と民間事業者の義務
不当な差別的取り扱いをすることは、国の行政機関、地方公共団体も民間事業者も禁止されます。
合理的配慮については、国の行政機関、地方公共団体は必ず行う法的義務ですが、民間事業者はできるだけ行う努力義務です。
障害を理由とする差別があったときには
行政機関の相談窓口に申し出てください。内容に応じて、行政相談委員による行政相談や、法務局、地方法務局、人権擁護委員による人権相談などさまざまな制度により対応しています。
また民間事業者によって繰り返し障害を理由とする差別が行われ、自主的な改善がされない場合は、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し報告を求めることや、助言、指導、勧告を行うことになっています。
障害者差別解消法Q&A
質問1.
合理的配慮の具体的な例を教えてほしい。
回答1.
個別のケースで異なります。典型的な例としては、車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをすることや窓口で、筆談や読み上げなど、障害のある人の障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応するなどが挙げられます。
質問2.
日常生活で個人的に障害のある人と接するときもあてはまりますか。
回答2.
個人的な関係は対象にはなりません。この法律では国の行政機関・地方公共団体、民間事業者を対象にしており、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは対象にはなりません。
質問3.
雇用における差別もこの法律の対象ですか。
回答3.
雇用については障害者雇用促進法に定められています。雇用の分野における差別については、相談や紛争解決の手段を含め、障害者雇用促進法に定めるところによります。
障害を理由とする差別を解消するための岩国市職員対応要領
本市におきましても、障害を理由とする差別の解消に関して、市の職員がその事務または事業を行うに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた市の職員対応要領を策定しました。
ダウンロード:障害を理由とする差別を解消するための岩国市職員対応要領 (Wordファイル)(29KB)
卓上型対話支援システム「コミューン」を設置しました
岩国市障害者支援課では、差別解消法における合理的配慮の一環として、平成28年4月に、卓上型対話支援システム「コミューン」を設置しました。
※卓上型対話システム「コミューン」とは・・・話者の声を高性能マイクで集音し、聴者側の小型スピーカーから聴き取りやすいクリアな音声を発するものです。話者の音声を大きくするのではなく明瞭にすることで、聴者が聴き取りやすくなり、コミュニケーションを円滑にします。
卓上型対話支援システム「コミューン」導入の様子

障害者差別解消法リーフレット
ダウンロード:内閣府 広報用リーフレット (PDFファイル) 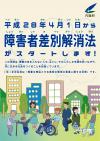
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
