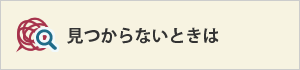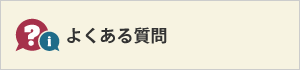野生鳥獣対策
野生鳥獣対策
私たちの生活圏に野生鳥獣の出没が増加した原因
本市の大部分は中山間地域であることから、豊かな自然に恵まれている反面、野生鳥獣の出没や野生鳥獣による農林業被害、生活環境被害の相談が多くあり、その深刻化が心配されています。
原因として考えられるのは、まず、緩衝帯の消失です。これまで人の生活圏と野生鳥獣が棲む「奥山」との間にあって、緩衝地帯の役割を果たしていた「田畑などの農地」や「里山」等が、人口減少や農林業の衰退などによって消失し、藪や山に戻ったことで、人の生活圏と山が隣り合わせになってしまいました。これにより、人の生活圏へ野生鳥獣が出没しやすい環境になってしまいました。
次に、野生鳥獣の生息域の拡大とそれによる頭数の増加です。前記の「農地」や「里山」の消失と、それに伴う藪や山林面積の増加は、野生鳥獣の生息域の拡大と頭数の増加に直結します。
そして、人の生活圏の中にある餌の存在です。野生鳥獣が人の生活圏へ出没しやすくなったことで、鳥獣被害防止対策を行っていない農地や家庭菜園などでは、簡単に農作物や果実などが食べられてしまうようになってしまいました。野生鳥獣は生きていくために餌に非常に執着します。野菜や果実は野生鳥獣にとってはご馳走ですので、それを狙って繰り返し出没しますし、地域に居ついてしまい繁殖すれば出没個体は年々増加していきます。
こういったことが原因で、私たちの生活圏に野生鳥獣の出没が増加してしまっていると考えられています。
人の生活圏へ出没すると様々な被害をもたらす野生鳥獣ですが、一方、命ある生き物でもありますので、むやみやたらに捕獲出来ないよう法律によって守られています。まずは人間の側で出来る対策をしっかり行い、被害を防止しましょう。
鳥獣被害防止対策を行う前に
普段の生活の中で野生鳥獣を見つけても、かわいいからといって餌をあげることは絶対にしないでください。人馴れを起こし、将来的な被害を発生させる原因になります。
鳥獣被害防止対策の基本(1)
被害をもたらしている加害鳥獣を特定し、その生態を知り、その鳥獣に合った被害防止対策を行いましょう。
鳥獣被害防止対策の基本(2)
被害防止対策にかかわる人たちとその役割を確認しましょう。
⑴農地や宅地などの土地を守るのは、所有者の責務です。(自助)
⑵地域一体で被害防止対策を行うとより効果的になります。(共助)
野生鳥獣は動き回る動物です。一人だけで対策を行っても、通常、被害はそれ以外の土地にも広範囲に及んでいきます。そのため、鳥獣被害防止対策は地域の皆さんで一体となって行うのがより効果的な対策となります。地道ですが、一番効果的ですので、皆さんで声を掛け合って対策を行ってください。
⑶市や県、国は、補助制度や支援策で個人や地域での取り組みを支援します。(公助)
鳥獣被害防止対策の基本(3)
できる対策を行いましょう。
前記の出没が増加した原因の中でも、容易に対策が行えるものと対策が難しいものがあります。人口減少、農林業の衰退する中で、田畑などの農地を再び緩衝帯として復活させ、森林面積を減少させていくことは非常に難しい解決方法ですし、長い時間も必要です。
また、それに伴う鳥獣の生息域と生息数を縮小・減少させていくことも同様に難しい解決方法です。
しかし、人の生活圏から野生鳥獣の餌となるものをなくしていくことはこれらに比べれば容易に行える対策です。こういった対策からしっかり行っていきましょう。
市では野生鳥獣の被害防止対策を「生息地管理」「防除」「捕獲」の3つに類型化し、特に出没予防対策となる「生息地管理」「防除」に力を入れて、対策の普及啓発を行っています。
生息地管理
人家や農地周辺などを含む野生鳥獣の生息地を適切に管理・整備すること、あるいは野生鳥獣の生息地と農地との間に緩衝地帯を設けることなどによって、農地や集落への出没を減少させ、被害を減らすことを言います。
これは医学で例えると「予防」に当たります。
具体的な生息地管理の方法は以下となります。
【人の生息域の中の餌をなくす対策】
・野菜クズを自宅や農地周辺に放置せず回収する。
・落ちて放置された柿や栗などの果実を定期的に回収する。
・収穫していない野菜の除却、放任果樹の枝打ち、伐採をする。
・生産している野菜や果実をこまめに収穫する。
・墓地の供え物等は持ち帰る。
【餌に近寄る野生鳥獣の隠れ場所をなくす対策】
・耕作放棄地や藪の草刈りを行う。
・自宅や農地の周辺の樹木を伐採し、緩衝帯を整備する。
不要なものは手放す、使うものはしっかり手入れするといったメリハリをつけた管理が重要です。
すべてを完全に管理することは難しいですので、できるところから始めましょう。
野生鳥獣の生態や特徴を踏まえ、人の生活圏へ出ていきたいと思わせる原因を1つでも取り除き、野生鳥獣にとって魅力のない空間を作りましょう。
市では、緩衝帯の整備や放任果樹の伐採を推奨しています。
・地域が育む豊かな森林づくり推進事業(やまぐち森林づくり県民税)<外部リンク>
(参考:令和3年度実績報告)<外部リンク>
防除
個人や集落で鳥獣の追い払いや侵入防止柵の設置を行うことにより、農地や宅地などへの侵入を防止することを防除といいます。
医学で例えると、鳥獣被害に遭う前の「予防」や、被害に遭った場合の「治療」に当たります。
具体的な防除の方法は以下となります。
【野菜や果樹への出没を追い払う対策】
・爆竹
・ロケット花火
山火事に十分注意し、対象獣種によって使い分けてください。
【農地や果樹園、家庭菜園への侵入を防止する対策】
・ワイヤーメッシュ柵
・電気柵(設置・管理には十分ご注意ください。)
・金網柵
・電気ネット柵
・トタン
・ネット
・防鳥ネット
柵には様々な種類がありますので、対象獣種によって使い分けてください。
不要なものは手放す、使うものはしっかり守るといったメリハリをつけた管理が重要です。
市では、柵の設置や追い払い用具の購入に支援を行っています。
・個人や集落などで行う農地の防除:鳥獣害防止対策事業補助金(市補助金)
・集落などで行う農地の防除:鳥獣被害防止対策総合交付金(国庫交付金)
侵入防止柵設置に当たっての注意点 (PDFファイル)(1.71MB)
侵入防止柵を定期的に点検しましょう (PDFファイル)(236KB)
捕獲
「生息地管理」や「防除」を行っても被害が減らない場合に限り、許可を得た上で有害鳥獣の捕獲を行うことができます。
・捕獲を行う場合は、原則「狩猟免許」が必要です。免許の取得などについては、山口県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
・捕獲許可については、下記ホームページをご参照し、事前にご相談願います。
山口県ホームページ<外部リンク>
「イノシシ捕獲用箱わな」または、「ヌートリア等捕獲用小型箱わな」の貸し出し
お問い合わせ先
•岩国市役所 農林振興課 0827-29-5170
•由宇総合支所 農林建設課 0827-63-1114
•周東総合支所 農林課 0827-84-1117
•美和総合支所 農林建設課 0827-96-1112
•錦総合支所 農林建設課 0827-72-2116