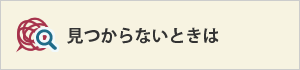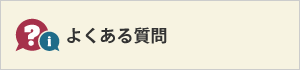サルの生態と対策
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月18日更新
生態
●大きさ
成獣は頭胴長50cm程度、体重10kg程度です。
●食性
植物性の強い雑食性(人が食べるものはサルも食べる)、タケノコや昆虫なども食べます。
●行動
早朝と夕方が採食のピークで、日の出から日没までの明るい時間だけ活発に行動し、夜間は活動しません。群れにより集団で行動し、決まった行動範囲の中で周期的に動きます。群れはメスと子どもを中心に構成され、十数頭から百頭を超えることもあります。オスは大人になると群れを離れて単独で行動したり、他の群れに移ったりします。また、高い学習能力を持ち、集落内の食べられるものを少しずつ覚えていきます。木登りが得意です。
●繁殖
概ね5歳以上は出産可能。2~3年に1回程度出産します。1度に1頭出産。寿命は20歳前後。
●特徴
記憶力は抜群で、一度味わった恐怖体験を忘れません。場所や状況も覚えています。
土地への執着は深いですが、群れ同士のバランスが崩れたり、環境に大きな変化があれば新しい土地に適応する柔軟さもあります。
新しいものや状況、場所を警戒しますが、いったん慣れると大胆に行動します。「人慣れ」が進むと追い払うのが難しくなります。
長距離を走るのは苦手で、安全な場所から離れることを嫌がります。
群れで行動するので、数頭が柵越えできて餌にあり付けても他のサルが入れないとその餌場を諦めます。
成獣は頭胴長50cm程度、体重10kg程度です。
●食性
植物性の強い雑食性(人が食べるものはサルも食べる)、タケノコや昆虫なども食べます。
●行動
早朝と夕方が採食のピークで、日の出から日没までの明るい時間だけ活発に行動し、夜間は活動しません。群れにより集団で行動し、決まった行動範囲の中で周期的に動きます。群れはメスと子どもを中心に構成され、十数頭から百頭を超えることもあります。オスは大人になると群れを離れて単独で行動したり、他の群れに移ったりします。また、高い学習能力を持ち、集落内の食べられるものを少しずつ覚えていきます。木登りが得意です。
●繁殖
概ね5歳以上は出産可能。2~3年に1回程度出産します。1度に1頭出産。寿命は20歳前後。
●特徴
記憶力は抜群で、一度味わった恐怖体験を忘れません。場所や状況も覚えています。
土地への執着は深いですが、群れ同士のバランスが崩れたり、環境に大きな変化があれば新しい土地に適応する柔軟さもあります。
新しいものや状況、場所を警戒しますが、いったん慣れると大胆に行動します。「人慣れ」が進むと追い払うのが難しくなります。
長距離を走るのは苦手で、安全な場所から離れることを嫌がります。
群れで行動するので、数頭が柵越えできて餌にあり付けても他のサルが入れないとその餌場を諦めます。
被害対策
●対策を行う前に
普段の生活の中で、子ザルや親ザルを見つけても、かわいいからといって餌をあげることは人馴れを起こし、将来的な被害を発生させる原因になりますので絶対にしないでください。
●対策(1)「生息地管理」
サルの出没対策の中で、基本的で最も有効な対策は、集落内に餌となるものを無くしておくことです。
集落内にサルの餌となるものが無ければ、サルは出没しても集落周辺には居つきません。
何の対策もせずに餌がある状況でその他の対策を行っても、別の群れや個体が現れて同じ被害が繰り返されてしまうだけです。
普段から、集落内に餌となるものを無くしておきましょう。(以下は、その対策の具体例です。)
・生産、収穫していない果樹(放任果樹)は枝打ちや伐採を検討しまし ょう。
・生産、収穫していない農作物は除却を検討しましょう。
・生産、収穫している果樹や農作物は侵入防止柵の設置や早めに摘み取るといった対策を行いましょう。
・農地、人家周辺などの屋外に生ごみや野菜くずを撒かない、置かないようにしましょう。
・農地や人家周辺の草の刈り払いや木の伐採などにより、耕作放棄地や藪を無くして、サルの隠れ場所を無くし、農地や人家へサルを近づけないようにしましょう。
特にサルが出没する地域で、人家の裏の木の枝が人家の屋根にかかってしまっている場合は、サルが木伝いに屋根に登り、瓦をずらしたり、太陽光発電設備を壊す恐れもありますので、日ごろから枝打ちや伐採を検討しましょう。
●対策(2)「防除」
地域で追い払いを行いましょう。サルの天敵は人間です。侵入したところを脅かされるなど、怖い目にあうことの多い集落は次第に避けるようになります。地域の複数人で協力して、爆竹や花火等による追い払いを継続的に行うことが、地道ですが有効な対策です。(使用に際しては、爆竹や花火等に記載されている取扱説明書をよく読み、火災や事故の無いよう注意して行ってください。)
傘やほうき等を振り回すことにより追払いを行うことも有効です。
威嚇を行い、サルに安心して行動できる場所ではないことを認識させることが重要なので、なるべく多くの人が集まり、追い払いを行いましょう。
農地へ侵入防止柵を設置するのも一つの方法です。周囲の樹木や建物から飛び込んで柵を乗り越えないよう、柵は周囲の樹木や建物から5m以上あけて設置しましょう。また、サルは柵を登ってしまうので、電気柵と組み合わせるなどの対策が必要です。
畑ごとネット等で覆ってしまう方法も有効です、
まずは、広い農地の中でも、絶対に守りたい箇所から設置し、徐々に設置場所を広げていきましょう。
普段の生活の中で、子ザルや親ザルを見つけても、かわいいからといって餌をあげることは人馴れを起こし、将来的な被害を発生させる原因になりますので絶対にしないでください。
●対策(1)「生息地管理」
サルの出没対策の中で、基本的で最も有効な対策は、集落内に餌となるものを無くしておくことです。
集落内にサルの餌となるものが無ければ、サルは出没しても集落周辺には居つきません。
何の対策もせずに餌がある状況でその他の対策を行っても、別の群れや個体が現れて同じ被害が繰り返されてしまうだけです。
普段から、集落内に餌となるものを無くしておきましょう。(以下は、その対策の具体例です。)
・生産、収穫していない果樹(放任果樹)は枝打ちや伐採を検討しまし ょう。
・生産、収穫していない農作物は除却を検討しましょう。
・生産、収穫している果樹や農作物は侵入防止柵の設置や早めに摘み取るといった対策を行いましょう。
・農地、人家周辺などの屋外に生ごみや野菜くずを撒かない、置かないようにしましょう。
・農地や人家周辺の草の刈り払いや木の伐採などにより、耕作放棄地や藪を無くして、サルの隠れ場所を無くし、農地や人家へサルを近づけないようにしましょう。
特にサルが出没する地域で、人家の裏の木の枝が人家の屋根にかかってしまっている場合は、サルが木伝いに屋根に登り、瓦をずらしたり、太陽光発電設備を壊す恐れもありますので、日ごろから枝打ちや伐採を検討しましょう。
●対策(2)「防除」
地域で追い払いを行いましょう。サルの天敵は人間です。侵入したところを脅かされるなど、怖い目にあうことの多い集落は次第に避けるようになります。地域の複数人で協力して、爆竹や花火等による追い払いを継続的に行うことが、地道ですが有効な対策です。(使用に際しては、爆竹や花火等に記載されている取扱説明書をよく読み、火災や事故の無いよう注意して行ってください。)
傘やほうき等を振り回すことにより追払いを行うことも有効です。
威嚇を行い、サルに安心して行動できる場所ではないことを認識させることが重要なので、なるべく多くの人が集まり、追い払いを行いましょう。
農地へ侵入防止柵を設置するのも一つの方法です。周囲の樹木や建物から飛び込んで柵を乗り越えないよう、柵は周囲の樹木や建物から5m以上あけて設置しましょう。また、サルは柵を登ってしまうので、電気柵と組み合わせるなどの対策が必要です。
畑ごとネット等で覆ってしまう方法も有効です、
まずは、広い農地の中でも、絶対に守りたい箇所から設置し、徐々に設置場所を広げていきましょう。
サルが出没しても地域に居つかないように、普段から地域で出来る対策をしっかり行ってください。
サル対策は常に現場にいる住民の方の対応が重要です。
市では、追い払いや侵入防止柵の設置等の被害対策に対して、下記の支援(補助)制度をご用意していますので、ご活用ください。
サル対策は常に現場にいる住民の方の対応が重要です。
市では、追い払いや侵入防止柵の設置等の被害対策に対して、下記の支援(補助)制度をご用意していますので、ご活用ください。
環境改善
市では、ご自宅や農地、果樹園などの周辺環境を改善していただくため、環境改善点検票を作成しました。
ご自宅などでの定期的な見直しにご活用ください。
なお、環境改善は、個人で行うだけでなく、自治会など多くの方で取り組むとより効果的です。
ご自宅などでの定期的な見直しにご活用ください。
なお、環境改善は、個人で行うだけでなく、自治会など多くの方で取り組むとより効果的です。
護身
人慣れを起こしたサルは、人間を自分より強そうか弱そうかで判断し、弱そうと判断した場合は攻撃的な対応をとることがあります。人慣れを起こしたサルに対しては、傘やホウキなどの柄の長い物を振り回して身を守りましょう。そもそも人慣れを起こさないよう、餌を与えない、餌を無くす、餌が得られないようにする、追い払いを行うなどの予防的な対策をしっかり行うことが重要です。
支援(補助)制度
パンフレット
モンキードック
モンキードッグガイドライン(山口県ホームページ)<外部リンク>