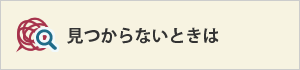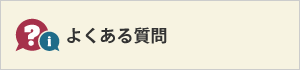介護保険の加入対象者と保険料について
介護保険の加入対象者と保険料について
介護保険に加入する人は?
- 65歳以上の人全員(第1号被保険者)と、
- 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人(第2号被保険者)です。
|
介護保険は市町村が運営主体(保険者)となりますので、岩国市に住所のある第1号被保険者の人は、原則として、岩国市の介護保険に加入していただくことになります。 ※ 他市等の住所地特例対象者、適用除外施設入所者の方等を除きます。 |
第1号被保険者の保険料の計算方法は?
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の額は、市区町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された基準額をもとに、所得に応じて各市町村が条例によって定めます。この保険料の額は3年ごとに見直すことになっています。岩国市の令和6年度~令和8年度の保険料は次のとおりです。
|
段階 |
該当する人 |
年額 |
|
第1段階 |
・老齢福祉年金受給者で市民税非課税の人 ・生活保護受給者 ・市民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額(長期・短期譲渡所得の特別控除額を控除した額。以下同じ。)から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が年間80.9万円以下の人
|
19,836円 |
|
第2段階 |
市民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が年間80.9万円を超え120万円以下の人 |
33,756円 |
|
第3段階 |
市民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が年間120万円を超える人 |
47,676円 |
|
第4段階 |
市民税課税世帯で、本人に市民税が課税されていない人のうち、公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が年間80.9万円以下の人 |
62,640円 |
|
第5段階 |
市民税課税世帯で、本人に市民税が課税されていない人のうち、公的年金等収入額と合計所得金額から公的年金等雑所得を控除した金額の合計額が年間80.9万円を超える人 |
69,600円 |
|
第6段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間120万円未満の人 |
83,520円 |
|
第7段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間120万円以上210万円未満の人 |
90,480円 |
|
第8段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間210万円以上320万円未満の人 |
104,400円 |
|
第9段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間320万円以上420万円未満の人 |
118,320円 |
|
第10段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間420万円以上520万円未満の人 |
132,240円 |
|
第11段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間520万円以上620万円未満の人 |
146,160円 |
| 第12段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間620万円以上750万円未満の人 |
153,120円 |
| 第13段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間750万円以上1,000万円未満の人 |
160,080円 |
|
第14段階 |
本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が年間1,000万円以上の人 |
167,040円 |
介護保険料の算定について、詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険料の算定について (Wordファイル)(1.3MB)
第1号被保険者の保険料の支払い方法は?
老齢・退職・遺族・障害年金の額が、年間18万円以上の人は、年金から天引きされます(特別徴収といいます。ただし、65歳到達時や転入時には一定期間〔半年以上〕は納付書などで納めていただくことになります)。
それ以外の人は、納付書や口座振替により個別に納めていただくようになります(普通徴収といいます)。その場合、毎年6月から翌年3月までの10回で1年分(12か月分)を納めていただくようになります。
保険料を滞納した場合
保険料を完納した方との公平性を保つため、滞納期間が1年を超えるとサービスを利用したときの保険給付が償還払いとなり、サービス費の全額をいったん自己負担することになります。
また、滞納期間が1年6ヶ月を超えると保険給付の支払いが差し止められ、市は保険給付から滞納保険料を控除することができることになっています。
さらに、滞納期間が2年を超えると、一定期間、利用者負担が3割に引き上げられます。(平成30年8月からは、利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。)
第2号被保険者の保険料の支払い方法は?
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険など)の保険料として納めていただくことになっています。
たとえば、給与所得者の健康保険の場合、その人の給与に応じて額を計算し、健康保険料と一括して毎月の給与から差し引かれます。
なお、国保世帯の第2号被保険者の保険料は、介護分として所得割、均等割、平等割の3方式で計算し、国民健康保険の医療分等と合わせて支払うことになります。