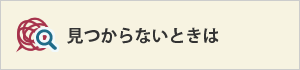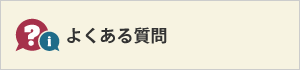中津居館跡の概要
中津居館跡(なかづきょかんあと)は14世紀頃に岩国地域を治めた有力者が築いたとみられる居館(きょかん)の跡です。
居館とは、有力者が住んだ屋敷のことで、居館の内部には、住居以外に政治を行う施設や客人を迎える施設などが設けられました。また、これらの施設を囲む土塁(どるい)と、土塁の外に堀を設けて、容易に居館内に近づけないようにしていました。
現地には幅15~20メートルの土塁の基底部が、東西約120~140メートル、南北約130~170メートルにわたって残っています。当時の居館の規模は館主の社会的地位に制約されましたが、中津居館跡の規模は守護大名大内氏の居館(山口市)に匹敵する規模があり、大変規模の大きい居館ということができます。
岩国市教育委員会は、平成20~22年度に中津居館跡の発掘調査を行いました。発掘調査の結果、居館の内部で、大型の掘立総柱建物跡や土師器(はじき)を大量に埋めた一括廃棄土坑(いっかつはいきどこう)などが発見され、地下の遺跡が良好な状態で保存されていることが確認されました。また、土塁(どるい)の断ち割り調査によって、特長的な土塁の構造が明らかになりました。
遺跡の概要
遺跡名
中津居館跡(なかづきょかんあと)
所在地
山口県岩国市楠町三丁目地内
種別
居館跡
時代
中世
規模
東西・・・約120~140メートル
南北・・・約130~170メートル(いずれも土塁の外側を結んだ距離)
土塁と居館内部を合わせた面積・・・約20,000平方メートル
築造主
弘中氏か
主な遺構
- 土塁
- 大型掘立総柱建物跡(9.6×9.6メートル以上)1棟
- 土師器一括廃棄土坑1基
- 堀状遺構2ヵ所
ほか
中津居館跡の空中写真(上が北)。ピンクで囲んだ線が、現地に残る土塁の外側のライン。