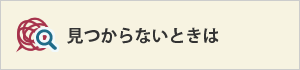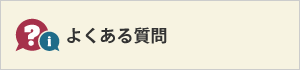中津居館跡発掘調査の主な成果(平成20-23)
平成20~23年度に行われた発掘調査の主な成果をご紹介します。
大型掘立総柱建物跡(おおがたほったてそうばしらたてものあと)1棟

赤丸で囲った所が建物跡の柱穴および柱穴の底に据えられた礎石。柱と柱の間隔は約2.4mあり、現時点で少なくとも9.6m×9.6mの規模があった事がわかっています。建物の柱穴は、掘った穴の底に礎石を置く、「地下式礎石」と呼ばれる方法がとられていました。
土師器一括廃棄土坑(はじきいっかつはいきどこう)1基
土師器(中世に用いられた素焼きの土器)の皿と椀、約70点がまとめて廃棄された土坑(地面を掘った穴)が見つかりました。この中には吉備地方(現在の岡山県南部辺り)産の土器も含まれており、器の形や特徴から14世紀前半に作られた土器であることがわかりました。 写真左上の石は大型掘立総柱建物の礎石の一つです。
土塁
中津居館跡の土塁は、基底部の幅が大きいところで20mに達する大規模なものです。今回3ヵ所で土塁の断ち割り調査を行ったところ、土塁外側に一抱え程の花こう岩を大量に埋めて土塁を強固に築いた構造が明らかになりました。
北土塁の断ち割り。奥の石は土塁外側の補強構造部分。
南土塁の断ち割り。 写真奥の土塁外側だけに花こう岩が大量に埋め込まれている。
堀状遺構(ほりじょういこう)
北土塁の外で、地面を大きく掘り込んだ形跡が確認されました。
また、土塁外側付近の地下には、大型の石で補強した土塁の基礎部分が確認されました。
手前が出土した土塁の基礎部分。上の石垣は現地に残る土塁。
現地に行かれる方へ
中津居館跡は市の所有する土地ではありません。現地に行かれる際は次のような点にご注意ください。
- 無許可で私有地に立ち入ることが無いように充分ご注意ください。
- 付近には駐車場がありません。また、周辺は道幅が狭いため車での見学はお勧めできません。
- 発掘調査現場は埋め戻されているため出土状況を見学することはできません。