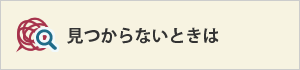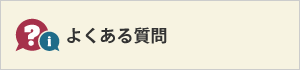2月給食メニューフォト(後半)
献立表
フォト
2月15日
・ごはん、高野豆腐の卵とじ、磯香和え、牛乳
高野豆腐は、豆腐を凍らせて作ります。
地域によって「凍り豆腐」や「凍み豆腐」と呼ばれます。
日本に昔から伝わる保存食で、今から約800年前に考えられたといわれています。
戦国武将の武田信玄は、軽くて栄養豊富な高野豆腐を戦に携帯する食べ物として使用していたそうです。
平成になると、宇宙食として使用され注目されました。
2月16日
・ごはん、魚の唐揚げ梅みそがけ、小松菜のごま和え、けんちん汁、牛乳
魚へんに雪と書く「鱈」は、冬の北海道を代表する魚の一つです。
軟らかく淡白な身で、どんな料理にも合います。
お腹いっぱい食べることを「たらふく食べる」と言いますが、これは、たらが卵を産む時期になると、カニやエビ、イカ、カレイなど身近な生き物を何でも食べてしまうほど大食いであることに由来しています。
2月17日
・コッペパン、ビーフシチュー、れんこんサラダ、牛乳
今日のビーフシチューに使っているお肉は、山口県産の和牛です。
肉のうま味が溶け込んで、とてもおいしいシチューになっていると思います。
また、サラダは岩国れんこんを使用したれんこんサラダです。
給食で使用している岩国れんこんはとても柔らかく、甘みがあります。
2月18日
・ごはん、さけの塩焼き、ごま酢和え、筑前煮、牛乳
筑前煮は、元々は筑前地方、現在の福岡県北部で作られていたものです。
地元では筑前煮とは言わず、「がめ煮」と呼ばれています。
がめ煮という名前にはいくつか説があり、博多の方言で「寄せ集める」という意味の「がめくりこむ」から名前がついたという説と、豊臣秀吉が朝鮮に出兵するときに博多に立ち寄り、スッポンをつかまえて野菜と煮たことから、スッポンの博多弁「がめ」からきたという説があります。
2月19日
・ごはん、豚肉のしょうが炒め、れんこんポテトサラダ、みそ汁、みかん、牛乳
今日の給食は、平田中学校1年2組が考えた、「冬の終わりを知らせるしょうが焼きメニュー」です。
ごはんの進むしょうが焼きを主菜とし、副菜はポテトサラダに岩国れんこんを入れ、工夫されています。
主食、主菜、副菜、汁物、果物がそろい、バランスの良い和食献立にまとまっています。
しっかり食べて元気に過ごし、暖かい春を迎えてほしいと思います。
2月22日
・ごはん、タレかつ、白和え、スキー汁、牛乳
今日の給食は、新潟県の郷土料理です。
新潟県のかつ丼は、卵でとじたかつ丼ではなく、揚げたてのカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせ、ご飯の上にのせたシンプルなタレかつ丼のことを指すそうです。
スキー汁は、明治時代に上越(じょうえつ)地方にスキーが伝えられたときに生まれた料理のようです。大根やにんじんを短冊切りにして、スキーの板を表しています。
2月24日
・コッペパン、いちごジャム、野菜たっぷりスープ、ごぼうサラダ、牛乳
野菜たっぷりスープには、旬の白菜をはじめ、野菜がたっぷり入っています。
白菜は約95%が水分ですが、ビタミンCやカリウム、カルシウム、鉄などが含まれています。
寒い冬には体を温める食べ物として重宝されます。
まだまだ寒い日もありますので、体を温める食材をしっかり食べて、元気に過ごしましょう。
2月25日
・ごはん、さばの塩焼き、卯の花炒り煮、かきたま汁、牛乳
卯の花は、おからの別名で、豆腐をつくるときに豆乳をしぼった残りかすです。
食物繊維、カルシウム、たんぱく質が多く含まれ、とても栄養のある食品です。
おからの白さが、初夏に白い花を咲かせる卯の花の色と似ていることから「卯の花」という呼び名になったようです。
古くから日本で食べられてきた食材のひとつです。
2月26日
・ごはん、イワシイワシれんこん、即席漬け、豆腐汁、ぽんかん、牛乳
給食の人気メニューのひとつに、チキンチキンごぼうやチキンチキンれんこんがありますが、今日はこれらのメニューをアレンジした「イワシイワシれんこん」を出しています。
魚が苦手な人でも食べやすい味付けで、地元特産の岩国れんこんを食べることもできます。
いわしには、生活習慣病の予防に効果のあるドコサヘキサエンサン、エイコサペンタエンサンという成分が含まれています。
青魚を食べないと不足してしまうので、日頃の食生活でも青魚をしっかり食べましょう。
このページに関するお問い合わせ先
〒740-0032 山口県岩国市尾津町五丁目11番2号
岩国学校給食センター
Tel:0827-34-1212
Fax:0827-32-2400