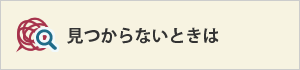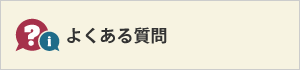道路こぼればなし1

1.錦帯橋は市道?
岩国で有名なものはいろいろあると思いますが、その中でも一番有名なのは、やっぱり錦帯橋ではないでしょうか。
錦帯橋は、現在、国指定の名勝として文化財となって
いますが、延宝元年(1673年)に当時の岩国藩主(領
主)であった吉川広嘉によって創建されました。創建以
降、2度石組橋脚が流失しましたが、木造部分を定期的
に架け替え続けられ、現在のものは平成13~15年に架
け替えられました。
この橋は、創建以来、橋の両側に橋守が設けられ橋の
保護と通行人の監視を行い、また横山側城内入口に大門
を設け衛士番卒を置いて、通行者を規制していたものと
考えられています。旅人等他藩の者はもとより、藩内の
者も通行が厳しく規制されていたようです。
しかし、他藩の者でも岩国藩に申し入れをすることにより、許可が出されたものもあったようですが、町奉行その他役人衆が案内に出向いてそのまま同行し、自由に通行することは許可されていなかったようです。
時代が下り、文化(1804年~)、文政(1818年~)の頃には規制も大分緩和され、錦帯橋を訪れる旅人が増え、天保(1831年~)には、外来客が橋上を賑わすようになったそうです。しかし、橋上に長く立ち止まること等は許されず、自由ではなかったようです。
明治(1868年~)になり、廃藩後は、橋守も廃止され自由な通行ができるようになり、車馬の通行が出来ない橋ではありますが国道に編入されました。
ただ、明治25年(1892年)に岩国町が、県に「橋の腐朽甚だしいため、空軽車、馬の通行を禁止」するよう申請し、県より「荷客を搭載した車は、現に通行してないにも関わらず、国道で空車馬の往来まで禁止するのは適当でない」と承認されなかったこともあったようで、人や荷を乗せない車や馬の渡橋についてはよく分かっていません。
大正4年(1915年)に臥龍橋が国道になったことにより、錦帯橋は岩国町の町道になり、大正11年(1922年)には「史跡名勝天然記念物保存法」により「名勝」として指定・保護され文部大臣の管轄となりました。これにより、車馬の通行が禁止され、橋の現状を害する行為が改めてはっきりと禁止されました。
昭和15年(1940年)の岩国市制施行とともに錦帯橋も市道となりました。その後、昭和40年(1965年)の錦城橋の完成により市道認定が解除されるまでの間、市道として多くの人が自由に行き来していました。(現在は、架け替え・維持経費のために有料となっています。) 参考文献「名勝錦帯橋のはなし」、「錦帯橋史」