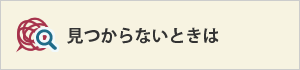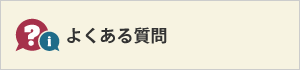ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護指定基準
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※介護予防なし)
【ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設】
| 事業内容 |
1.基本方針 ア.入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、居宅生活への復帰を念頭において、入居前の居宅生活と入居後の生活の連続性に配慮しながら、各ユニットにおいて入居者相互の社会的関係の構築、自律的な日常生活を支援する。 イ.地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 |
||
|---|---|---|---|
|
申請者要件 |
老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下であるものの開設者 |
||
| 人員基準 | 管理者 | 専ら職務に従事する常勤の者であること。ただし、当該施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は、管理者としての職務を除く。)に従事することができる。 | |
|
|
1.医師 入所者の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。 (サテライト型居住施設は、本体施設の医師が本体施設及びサテライト型居住施設の入所者等の処遇を適切に行うことが認められる場合は、置かないでも可。) 2.生活相談員 常勤1以上 (サテライト型居住施設は、常勤換算方法で1以上。) (サテライト型居住施設は、常勤換算方法で1以上の基準を満たしていれば、非常勤の者であっても差し支えない。) 3.介護職員または看護職員 ア.総数 常勤換算方法で、入所者の数が3またはその端数を増すごとに1以上(1以上は常勤。) イ.介護職員 1以上は常勤。 ウ.看護職員 1以上(1以上は常勤。) (サテライト型居住施設は、常勤換算方法で1以上。) (サテライト型居住施設は、常勤換算方法で1以上の基準を満たしていれば、非常勤の者であっても差し支えない。) *看護職員とは、看護師もしくは准看護師 4.栄養士または管理栄養士 1以上 (隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士・管理栄養士との兼務や地域の栄養指導員との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合、置かないでも可) (サテライト型居住施設は、本体施設[指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院または病床数100床以上の病院に限る。]の栄養士または管理栄養士により、本体施設及びサテライト型居住施設の入所者等に適切にサービスが提供されると認められる場合は、置かないでも可。) 5.機能訓練指導員 1以上(当該施設の他の職務と兼務可。) (サテライト型居住施設は、本体施設[指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または介護老人保健施設に限る。]の機能訓練指導員または理学療法士・作業療法士により本体施設及びサテライト型居住施設の入所者等に適切にサービスが提供されると認められる場合は、置かないでも可。) *機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)』とする。 ただし、日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生活相談員または介護職員が兼務可。 6.介護支援専門員 1以上(1以上は常勤。当該施設の他の職務と兼務可。) (増員に係る非常勤の介護支援専門員を除き、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は不可。) (サテライト型居住施設は、本体施設[指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院または指定介護療養型医療施設に限る。]の介護支援専門員により、本体施設及びサテライト型居住施設の入所者等に適切にサービスが提供されると認められる場合は、置かないでも可。) 注1)入所者の数は、前年度の平均値。新規に指定を受ける場合は推定数。 注2)常勤換算方法とは、従業者の勤務延時間数の総数を、常勤の従業者の勤務すべき時間数で除し、常勤の従業者の員数に換算する方法。 注3)指定(介護予防)短期入所生活介護事業所との併設の場合は、当該併設事業所の医師を置かないことができる。 注4)指定通所介護事業所、指定(介護予防)短期入所生活介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所との併設の場合は、当該併設事業所の生活相談員、栄養士または機能訓練指導員は置かないことができる。 注5)併設される指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の定員は、当該施設の入所定員と同数を上限とする。 注6)指定小規模多機能型居宅介護事業所との併設の場合は、当該施設の介護支援専門員を置かないことができる。 注7)指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所との併設の場合は、各々の基準を満たす従業者を置いているときは、当該施設の従業者は、当該指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事できる。 ※ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、常時1人以上の介護職員を介護に従事させること。 ※ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者に対し適切なサービス提供ができるよう、従業者の勤務体制を定めておくこと。 <従業者の勤務体制を定めるに当たっての職員配置は次のとおりとする。> 1.昼間:ユニットごとに常時1人以上の介護職員または看護職員を配置すること。 2.夜間及び深夜:2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 3.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 |
||
|
設備基準 |
1.ユニット:施設の全部において少数の居室と共同生活室によって一体的に構成される場所 ア.居 室(使い慣れた家具等を持ち込むことができる個室) (a)定員:一の居室につき1人 ただし、サービス提供上必要な場合は2人とすることができる。 (b)居室はいずれかのユニットに属するものとし、共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、1ユニットの入居定員は、原則として概ね10人以下とし、15人を超えないものとすること。 (c)床面積:一の居室につき10.65平方メートル以上 ただし、(a)のただし書き場合(2人居室)は、21.3平方メートル以上 ※ユニットに属さない居室を改修したものは、10.65平方メートル以上、(a) のただし書き場合(2人居室)は、21.3平方メートル以上とし、入居者同士の視線の遮断が確保されていれば、居室の壁は天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。 ※居室内に洗面設備が設けられているときはその面積を含み、居室内に便所が設けられているときはその面積を除く。 (d)ブザーまたはこれに代わる設備を設けること。 イ.共同生活室(居宅での居間に相当する部屋) (a)いずれかのユニットに属し、当該ユニットの入居者の交流、共同生活にふさわしい形状とすること。このための要件は次のとおりとする。
(b)床面積:2平方メートル×(属するユニットの入居定員)以上 (c)必要な設備および備品を備えること。 ウ.洗面設備 (a)居室ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数を設けること。 (b)要介護者が使用するのに適したものとすること。 エ.便所 (a)居室ごとに設けるか、共同生活室ごとに適当数を設けること。 (b) ブザーまたはこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者の使用に適したものとすること。 2.浴室:要介護者の入浴に適したものとすること。 3.医務室 ア.医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。 イ.入居者の診療に必要な医薬品及び医療機器を備えること。 ウ.必要に応じて臨床検査設備を設けること。 ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設は、医務室を必要とせず、入居者の診療に必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。 4.廊下幅 1.5メートル以上。ただし、中廊下の幅は1.8メートル以上。 なお、廊下の一部の幅を拡張することで、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないときはこの限りでない。 5.消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 |
||
|
運営基準 |
内容及び手続の説明及び同意 提供拒否の禁止 サービス提供困難時の対応 受給資格等の確認 要介護認定の申請に係る援助 入退所 サービスの提供の記録 利用料等の受領 保険給付の請求のための証明書の交付 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針 地域密着型施設サービス計画の作成 介護 食事 相談及び援助 社会生活上の便宜の提供等 機能訓練 栄養管理 口腔衛生の管理 健康管理 入所者の入院期間中の取扱い 利用者に関する市町村への通知 緊急時等の対応 管理者による管理 管理者の責務 計画担当介護支援専門員の責務 運営規程 業務継続計画の策定等 勤務体制の確保等 定員の遵守 非常災害対策 衛生管理等 協力医療機関等 掲示 秘密保持等 広告 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 苦情処理 地域との連携等 事故発生の防止及び発生時の対応 虐待の防止 会計の区分 記録の整備 |
第3条の7(準用) 第3条の8(準用) 第133条(準用) 第3条の10(準用) 第3条の11(準用) 第134条(準用) 第135条(準用) 第161条 第3条の20(準用) 第162条 第138条(準用) 第163条 第164条 第141条(準用) 第165条 第143条(準用) 第143条の2(準用) 第143条の3(準用) 第144条(準用) 第145条(準用) 第3条の26(準用) 第145条の2(準用) 第146条(準用) 第28条(準用) 第147条(準用) 第166条 第3条の30の2(準用) 第167条 第168条 第32条(準用) 第151条(準用) 第152条(準用) 第3条の32(準用) 第153条(準用) 第3条の34(準用) 第154条(準用) 第3条の36(準用) 第34条第1~4項(準用) 第155条(準用) 第3条の38の2(準用) 第3条の39(準用) 第156条(準用) |
|