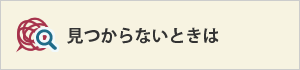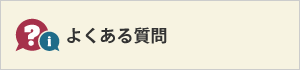認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護指定基準
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
|
事業内容 |
要介護者、要支援者(要支援2)であって認知症の状態にあるものについて共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。 |
||
|---|---|---|---|
|
申請者要件 |
法人 |
||
|
人員基準 |
代表者 |
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者もしくは訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、または保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、厚生労働大臣が定める研修~認知症対応型サービス事業開設者研修~を修了している者。 *基本的には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該当する。 |
|
|
管理者 |
1.共同生活住居ごとに、専ら職務に従事する常勤の者。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務、または他の事業所・施設等の職務に従事することができる。 2.特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修~認知症対応型サービス事業管理者研修~を修了している者。 *基本的には、各事業所の責任者を指す。 |
||
|
従業者 |
1.介護従業者 以下のとおりで、1以上は常勤。 ア.夜間および深夜の時間帯以外の時間帯(常勤換算方法) 共同生活住居ごとに利用者の数が3またはその端数を増すごとに1以上 イ.夜間及び深夜の時間帯 夜間及び深夜勤務(宿直勤務を除く。):共同生活住居ごとに1以上 *介護従業者は、資格等は必ずしも必要としないが、原則として、介護等に対する知識、経験を有する者であること。また、事業者は研修の機会を確保するとともに、資格を有する者やそれに類するものを除き、認知症介護に係る基礎的研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。 2.計画作成担当者 1以上。 事業所ごとに、保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって、計画の作成を 担当させるのに適当と認められ、専らその職務に従事する者で、厚生労働大臣が定める研修~「実践者研修」または「基礎課程」を修了している者。 *1以上は介護支援専門員とする。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の職務と兼務することができる。 注1)利用者の数は、前年度の平均値。新規に指定を受ける場合は推定数。 注2)常勤換算方法とは、従業者の勤務延時間数の総数を、常勤の従業者の勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で 除し、常勤の従業者の員数に換算する方法。 注3)指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所との併設の場合、各々の事業所が人員基準を満たす従業者を置いているとき、当該事業所の従業者は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所または当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。 注4)併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所または指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該事業所の効果的な運営を期待できる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、介護支援専門員を置かないことができる。 注5)介護支援専門員である計画作成担当者は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督すること。 注6)介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他認知症高齢者の介護サービス計画作成の実務経験を有すると認められる者であること。 |
||
|
設備基準 |
1.共同生活住居数:1以上3以下 2.入居定員:1の共同生活住居につき、5人以上9人以下 3.居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者の日常生活に必要な設備を設けること。 ア.居 室(一につき) (a) 定 員:1人(ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は2人とすることができる。) (b) 床面積:7.43平方メートル以上(和室であれば4.5畳以上) イ.居間および食堂 同一の場所とすること可。 4.利用者の家族との交流の機会確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地や住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。 |
||
|
運営基準 |
内容及び手続きの説明および同意 提供拒否の禁止 受給資格等の確認 要介護認定の申請にかかる援助 入退居 サービスの提供の記録 利用料等の受領 保険給付の請求のための証明書の交付 指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 認知症対応型共同生活介護計画の作成 介護等 社会生活上の便宜の提供等 利用者に関する市町村への通知 緊急時等の対応 管理者の責務 管理者による管理 運営規程 勤務体制の確保等 定員の遵守 業務継続計画の策定等 協力医療機関等 非常災害対策 衛生管理等 掲示 秘密保持等 広告 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止 苦情処理 調査への協力等 地域との連携等 事故発生時の対応 虐待の防止 会計の区分 記録の整備 |
第3条の7(準用) 第3条の8(準用) 第3条の10(準用) 第3条の11(準用) 第94条 第95条 第96条 第3条の20(準用) 第97条 第98条 第99条 第100条 第3条の26(準用) 第80条(準用) 第28条(準用) 第101条 第102条 第103条 第104条 第3条の30の2(準用) 第105条 第82条の2(準用) 第33条(準用) 第3条の32(準用) 第3条の33(準用) 第3条の34(準用) 第106条 第3条の36(準用) 第84条(準用) 第34条 第3条の38(準用) 第3条の38の2(準用) 第3条の39(準用) 第107条 |
|
|
《短期利用認知症対応型共同生活介護費施設基準》 1.当該指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営について3年以上の経験を有すること。 2.共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室等を利用するものであること。 3.利用者数は、一の共同生活住居で1名とすること。 4.利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に短期利用認知症対応型共同生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス計画において位置付けられていない短期利用認知症対応型共同生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合は、2、3にかかわらず事業所の共同生活住居ごとに定員数を超えて、短期利用認知症対応型共同生活介護を行うことができる。 ※当該利用者が利用できる個室を有する事。 5.あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。 ※4の場合、7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度とすること。 6.短期利用を実施するために十分な知識を有する介護従業者(認知症介護実務者研修のうち「専門課程」または認知症介護実践研修のうち「実践リーダー研修」若しくは「認知症介護実践リーダー研修」または認知症介護指導者養成研修を修了している者)が確保されていること。 |
|||