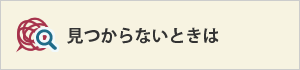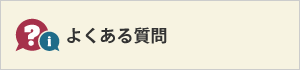小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護指定基準
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
|
事業内容 |
要支援者・要介護者について、その居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の有する能力に応じ、その居宅において自立した日常生活を営むことができるようにする。 |
||
|---|---|---|---|
|
申請者要件 |
法人であって、老人福祉法に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う者 |
||
|
人員基準 |
代表者 |
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、または保健医療サービスもしくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者で、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業開設者研修)を修了している者。 *基本的には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該当する。 |
|
|
管理者 |
1.専ら職務に従事する常勤の者。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務に従事することができる。 2.特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所等の従業者または訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了している者。 ※事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務、または併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)、介護医療院の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者または指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む。)、もしくは介護予防・日常生活支援総合事業(第一号介護予防事業を除く)に従事することができる。 *基本的には、各事業所の責任者を指す。 |
||
|
従業者 |
1.介護従業者:以下のとおりで、1以上は常勤。 ア.夜間および深夜の時間帯以外の時間帯(常勤換算方法) (1)通いサービス:利用者の数が3またはその端数を増すごとに1以上 (2)訪問サービス:1以上 イ.夜間および深夜の時間帯 (1)夜間および深夜勤務:1以上 (2)宿直勤務:当該宿直勤務に必要な数以上 *1以上は看護師または准看護師 *介護従業者は、資格等は必ずしも必要としないが、原則として、介護等に対する知識、経験を有する者であること。また、事業者は研修の機会を確保するとともに、資格を有する者やそれに類する者を除き、認知症介護に係る基礎的研修を受講させるための必要な措置を講じなければならない。 2.介護支援専門員:1以上 厚生労働大臣が定める研修(小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修)を修了している者。 ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の他の職務や、併設する施設等(「管理者」の項参照。)の職務と兼務することができる。 *介護支援専門員の業務
注1)利用者の数は、前年度の平均値。新規に指定を受ける場合は推定数。 注2)宿泊サービスの利用者がいない場合、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するための必要な連絡体制を整備しているときは、宿直勤務並びに夜間および深夜の従業者を置かないことができる。 注3)常勤換算方法とは、従業者の勤務延時間数の総数を、常勤の従業者の勤務すべき時間数で除し、常勤の従業者の員数に換算する方法。 注4)指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院との併設の場合、各々の施設等が人員基準を満たす従業者を置いているとき、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護職員はこれらの施設等の職務に従事することができる。 注5)上記注4に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所、指定認知症対応型通所介護事業所が同一の敷地内にある場合、各々の施設等が人員基準を満たす従業者を置いているとき、当該小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員はこれらの施設等の職務に従事することができる。 |
||
|
設備基準 |
1.登録定員:29人以下 *複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認めらない。 2.居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他サービス提供に必要な設備、備品等を備えること。 ア.居間および食堂 機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。なお、通いサービスの利用定員について15人を超えて定める場合は、居間および食堂を合計した面積は、通いサービスの利用定員×3平方メートル以上を確保する必要がある。 ※同一の場所とすることは可だが、それぞれの機能が独立していることが望ましい。 イ.宿泊室 (a)個室 (1)定員:宿泊室1に対し1人 ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。 (2)床面積:1の宿泊室につき7.43平方メートル以上 (b)個室以外 (1)床面積:合計で、概ね、7.43平方メートル×〔宿泊サービスの利用定員(通いサービスの利用定員の3分の1から9人までの範囲内で事業者が定める1日あたり利用者数の上限。)から個室定員を差し引いた数〕以上。 (2)構造:利用者のプライバシーが確保されたもの (3)プライバシーが確保されていれば居間も宿泊室の面積に含めて可。 3.設備は指定小規模多機能型居宅介護の専用でなければならない。 ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、この限りでない。 利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地や住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。 |
||
|
運営基準
|
内容及び手続きの説明および同意 提供拒否の禁止 サービス提供困難時の対応 受給資格等の確認 要介護認定の申請にかかる援助 心身の状況の把握 居宅サービス事業者等との連携 身分を証する書類の携行 サービスの提供の記録 利用料等の受領 保険給付の請求のための証明書の交付 指定小規模多機能型居宅介護の基本方針 指定小規模多機能型居宅介護の具体的方針 居宅サービス計画の作成 法定代理受領サービスに係る報告 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 小規模多機能型居宅介護計画の作成 介護等 社会生活上の便宜の提供等 利用者に関する市町村への通知 緊急時等の対応 管理者の責務 運営規程 勤務体制の確保等 定員の遵守 業務継続計画の策定等 非常災害対策 協力医療機関等 衛生管理等 掲示 秘密保持等 広告 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 苦情処理 調査への協力等 地域との連携等 居住機能を担う併設施設等への入居 事故発生時の対応 虐待の防止 会計の区分 記録の整備 |
第3条の7(準用) 第3条の8(準用) 第3条の9(準用) 第3条の10(準用) 第3条の11(準用) 第68条 第69条 第70条 第3条の18(準用) 第71条 第3条の20(準用) 第72条 第73条 第74条 第75条 第76条 第77条 第78条 第79条 第3条の26(準用) 第80条 第28条(準用) 第81条 第30条(準用) 第82条 第3条の30の2(準用) 第82条の2 第83条 第33条(準用) 第3条の32(準用) 第3条の33(準用) 第3条の34(準用) 第3条の35(準用) 第3条の36(準用) 第84条 第34条(準用) 第86条 第3条の38(準用) 第3条の38の2(準用) 第3条の39(準用) 第87条 |
|