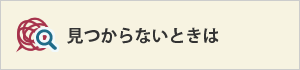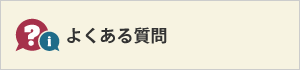定期巡回・随時対応型訪問介護看護指定基準
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※介護予防なし)
|
事業内容 |
(1)基本方針 居宅要介護者に対し、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回または随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指す。 (2)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期巡回サービス、随時対応サービス、随時訪問サービス、訪問看護サービスを提供すること。 |
||
|---|---|---|---|
|
申請者要件 |
法人 |
||
|
人員基準 |
管理者 |
専ら職務に従事する常勤の者であること。 ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務または他の事業所、施設等の職務に従事することができる。 |
|
|
従業者 |
(1) オペレーター(随時対応サービスとして、利用者またはその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者) ア 提供時間帯を通じて1以上確保されるために必要な数以上 ※午後6時から午前8時までの時間帯については、ICT等の活用により、事業所外においても、利用者情報の確認ができるとともに、電話の転送機能等を活用することにより、利用者からのコールに即時オペレーターが対応できる体制を構築し、コール内容に応じて必要な対応を行うことができると認められる場合は、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 イ 看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士または介護支援専門員でなければならない。 ※ただし、当該オペレーターがオペレーターとして勤務する時間以外の時間帯において、当該オペレーターまたは事業所の看護師等との密接な連携を確保することにより、利用者からの通報に適切に対応できると認められる場合は、サービス提供責任者として1年以上(介護職員初任者研修修了者及び旧訪問介護職員養成研修2級修了者にあたっては3年以上)従事した者をオペレーターとして充てることができる。 ウ 1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。 エ 原則として利用者からの通報を受ける業務に専従する必要があるが、利用者の処遇に支障がない場合は、当該事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所、指定訪問看護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務または利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 オ 当該事業所に次のいずれかの施設等が同一敷地内または道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所のオペレーターの業務に支障がないと認められる範囲内にある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、エの規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
カ 当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、エの規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 ※オペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 (2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上。 ※訪問介護員等 サービスの提供に当たる介護福祉士または介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。 (3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上。 ※ただし、利用者の処遇に支障ない場合、当該事業所の定期巡回サービスまたは指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができるほか、オペレーターが当該業務に従事することも差し支えない。 ※午後6時から午前8時までの時間帯については、利用者からの連絡を受けた後、事業所から利用者宅へ訪問するのと同程度の対応ができるなど、随時訪問サービスの提供に支障がない体制が整備されているのであれば、必ずしも事業所内で勤務する必要はない。 (4) 訪問看護サービスを行う看護師等 ア 保健師、看護師または准看護師 ・常勤換算方法で2.5以上 ・看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師または看護師でなければならない。 ・看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、当該事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 ※常時の配置を求めていないが、利用者の看護ニーズに適切に対応するため、常時、当該看護師のうち1人以上の者との連絡体制を確保しなければならない。 イ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 事業所の実情に応じた適当数 (5) 計画作成責任者 事業所ごとに、従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、利用者に対するサービス計画の作成に従事する者としなければならない。 |
||
|
設備基準 |
(1)事業運営に必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、サービス提供に必要な設備、備品等を備えること。 (2)利用者が円滑に通報し、迅速な対応を受けることができるよう、事業所ごとに、次に掲げる機器等を備え、必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし、アに掲げる機器等については、当該事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。 ア 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 イ 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 (3)利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう、利用者に対し、通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。 |
||
|
運営基準
|
内容及び手続きの説明及び同意 提供拒否の禁止 サービス提供困難時の対応 受給資格等の確認 要介護認定の申請に係る援助 心身の状況等の把握 居宅介護支援事業者等との連携 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 居宅サービス計画等の変更の援助 身分を証する書類の携行 サービスの提供の記録 利用料等の受領 保険給付の請求のための証明書の交付 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針 主治の医師との関係 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 同居家族に対するサービス提供の禁止 利用者に関する市町村への通知 緊急時等の対応 管理者等の責務 運営規程 勤務体制の確保等 業務継続計画の策定等 衛生管理等 掲示 秘密保持等 広告 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 苦情処理 地域との連携等 事故発生時の対応 虐待の防止 会計の区分 記録の整備 |
第3条の7 第3条の8 第3条の9 第3条の10 第3条の11 第3条の12 第3条の13 第3条の14 第3条の15 第3条の16 第3条の17 第3条の18 第3条の19 第3条の20 第3条の21 第3条の22 第3条の23 第3条の24 第3条の25 第3条の26 第3条の27 第3条の28 第3条の29 第3条の30 第3条の30の2 第3条の31 第3条の32 第3条の33 第3条の34 第3条の35 第3条の36 第3条の37 第3条の38 第3条の38の2 第3条の39 第3条の40 |
|
|
連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例 |
適用除外 指定訪問看護事業者との連携 |
第3条の41 第3条の42 |
|