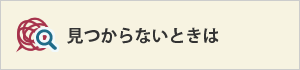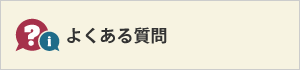岩国市キッズコーナー めいじからたいへいようせんそうまで
岩国は1889年(明治22年)町になり、1940年(昭和15年)市になりました。
岩国に鉄道がしかれたのは、1897年(明治30年)のことです。そのころは、ほとんどの家が農家でした。岩国駅のあたりも一面、わた畑やくわ畑が広がっていて、駅のホームからは、アシのしげる海岸線(かいがんせん)を見わたすことができました。駅前も、10数けんの家があるだけのさびしいところでした。鉄道がしかれたといっても、汽車に乗るのは遠くに行くときだけで、たいていは歩いていました。
1934年(昭和9年)に岩徳線(がんとくせん)が開通しました。それまでは、徳山へ行く時は、海岸ぞいの鉄道をつかいました。玖珂地域(くがちいき)や周東地域(しゅうとうちいき)の人が岩国に来る時は、欽明路(きんめいじ)のとうげを歩いてこえて来ていました。
また、新町(しんまち)から新港(しんみなと)まで路面電車(ろめんでんしゃ)が走っていましたが、かわりに省営(しょうえい)バス(今のJR)や町営バス(今の市営)が走るようになりました。
太平洋戦争(たいへいようせんそう)のころは、みんな戦争のために一生懸命でした。鉄道は、国鉄柳井線(こくてつやないせん)ができ、麻里布駅(まりふえき)とよばれていたのが、岩国駅になりました。
川下(かわしも)に海軍(かいぐん)の飛行場(ひこうじょう)がつくられたのもこのころです。
1945年(昭和20年)8月6日、広島に原子爆弾(げんしばくだん)が落とされました。それから1週間後の8月14日、岩国ははげしいばくげきにあい、岩国駅のあたりは大ひがいを受けました。 この戦争中のばくげきで、死んだ人やゆくえの分からない人が720人あまりもありました。
戦争が終わったあと、川下にあった飛行場は、連合国軍(れんごうこくぐん)の基地(きち)になり、さらに1958年(昭和33年)には、アメリカ軍の基地となりました。今は日本の自衛隊(じえいたい)もいっしょに使っています。