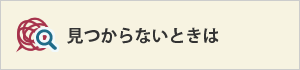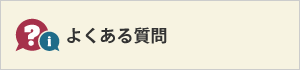岩国市キッズコーナー きっかわしがおさめたじだい
吉川氏(きっかわし)の先祖(せんぞ)は藤原氏(ふじわらし)といわれます。かつて駿河(するが(今の静岡県))入江庄吉河(いりえしょうきっかわ)に住み、その地名をもって「吉川」という名前にした吉川氏は、その後安芸(あき(今の広島県西部))に本きょをうつし、力を広げていきます。吉川の名前を天下に広めたのは、吉川元春(きっかわもとはる)です。この元春は「三矢(さんや)の教え」で有名な、毛利元就(もうりもとなり)の次男(じなん)です。
「三矢の教え」とは、毛利元就が、三人の子(毛利隆元(もうりたかもと)、吉川元春、小早川隆景(こばやかわたかかげ))を、死ぬ前にまくらもとに呼んで、「一本の矢はかんたんに折れるが、三本いっしょにした矢はなかなか折れない。このようにお前たち兄弟も力を合わせてやっていくことが大切(たいせつ)だ」と、協力(きょうりょく)する大切さを教えたというお話です。
元春、元長のあとをついだ広家(ひろいえ)は、1591年、豊臣秀吉(とよとみひでよし)から、出雲国(いずもこく(いまの島根県東部))冨田12万石(まんごく)の領主(りょうしゅ)となるように命じられました。やがて、1600年、関(せき)が原(はら)の戦いには、西軍(せいぐん)として参加した毛利輝元が負けたため、周防(すおう)3万石(のち6万石)に移されます。
岩国に着いた広家は、由宇(ゆう)に上陸(じょうりく)して、1602年、岩国を本きょと決めました。その後、吉川家は、明治維新(めいじいしん)までの260年間、この地で文化の香りの高い政治(せいじ)をおこないました。
岩国藩(いわくにはん)をはじめた吉川広家から数えて3代目が、広家の孫・広嘉(ひろよし)です。広嘉はもともと病気(びょうき)がちで体が弱く、京都(きょうと)に行って病気を治しているときに、京都の文化に親(した)しみ、またいろいろ学びました。読書に親しみ、武芸(ぶげい)を好み、学問と技術ごころを大切にする政策は、岩国の文化を始めた人として尊敬(そんけい)されています。また、「流れない橋・錦帯橋(きんたいきょう)」を作った人としても有名です。